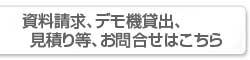経営最前線
 |  |
| Monthly Report 8月号/表紙と日本テレソフト記事内容 | |
■ 点字とともに広がる事業
小さな市場でいかにしてビジネスを成立させるか。㈱日本テレソフトは点字機器の分野において、新たにセット販売を行った。これにより採算がとれないといわれていた点字関連機器の販売を、ビジネスに結びつけることに成功した。
■ 点字を支える3製品のラインナップ
同社が最初に開発した製品は、点字作成システムである。パソコンに日本語の文章を入力すると、組み込まれている点訳ソフトによって、文字が自動的に点字に変換されるシステムだ。
次に同社が開発したのは、点字プリンターである。点字に変換された文章を、紙に凹凸をつけて点字として打ち出す。同社の製品は日本に広く普及している海外製品と違って、点字を打ち出す音が非常に静かである。点字と並べて墨字(インクで表示した文字)も打ち出せるので、障害者と健常者が一緒に文章を読み、コミュニケーションを図ることができる。
さらに、同社は点字読み取り装置を開発した。この装置ではまず、点字で打ち出された紙に光を当て、凹凸をスキャナーで読み取る。次にその凹凸を日本語の文章に変換してパソコンのディスプレイに表示する。これらの一連の機器を使えば、まったく点字を知らない人でも点字文章を作ったり読んだりできる。
現在、同社の点字機器の売り上げは約1億円にのぼる。ソフトウエア主体の会社である同社の年商の20%ほどを占め、事業の柱に成長している。
■ 小さな市場にビジネスチャンスを発見
国内に視覚障害者は約35万人いる。そのうち点字を解読できる人はわずか3万人ほどしかいないといわれる。また、同社が製品開発を始めた91年当時は、点字で情報を発信しようとする提供者の数は限られていた。そのために、点字用の製品を開発しても売り上げが伸び悩み、とても採算ベースに乗せることはできないと考えられていた。にもかかわらず、同社が3製品を自社開発したのには理由がある。
ワープロソフトを納品している取引先から、ワープロを使うように点字の文章を作れる装置がほしいと言わた金子社長は、まず、当時数少なかった国内点字機器メーカーの取り組み状況を調べ始めた。すると、ソフトメーカーは点訳ソフトだけをプリンターメーカーは点字プリンターだけを製造販売していた。その一方で使い手は、互換性を気にせず便利に使えるように、同じ会社から機器をまとめて購入したいと考えていることが分かった。使い手のニーズとメーカーの戦略がずれていた結果、販売の機会が広がらず、収益が上がらない状況になっていたのである。
そこで、点字文書の作成から印字、読み取りといった作業に合わせた点字機器を製造してセット販売すれば、既存のメーカーの差別化が図れると金子さんは考えた。また、1社ですべての製品をそろえれば、万一故障しても使用者は同社に連絡するだけで済み、非常に楽である。そこで同社は、この方法によって新規参入することにした。
後発メーカーである同社は、販売にあたって他社との違いをアピールするために、実演してみせた。盲学校や点字図書館などは全国に300ヶ所ほどあるが、この数なら限られた同社社員だけでも十分に回ることができた。こうして納入した盲学校や点字図書館から、役場などへ同社製品の噂が広まり、注文は増えていった。
使い勝手の良い同社の製品は、福祉関係だけでなく、それまで縁がないと考えられていたところにも需要を広げた。たとえば、航空会社では機内食のメニューの作成に、テーマパークではパレードの案内の作成に同社の製品一式が使われている。
■ 低価格化のための海外展開
「目が不自由な人のデジタルデバイトを少しでも解消したい」と話す金子さんは、新製品の開発にも余念がない。昨年には、インターネットにつないで点字を使って電子メールをやり取りしたり、障害者向けのホームページを閲覧したりできる装置を開発した。しかし、この装置や点字プリンターは、1台で60万近くするなど製品価格が高く、気軽に買えるというものではない。いかにして製品価格を下げるかが課題である。そこで同社では、海外に進出して市場を広げ、生産ロットを増やして単位当たりのコスト削減することにした。
プリンターについていえば、販売をなんかん1,000台まで増やすことができれば、原価を現在の7割程度に抑えられる。同社は、日本の30~40倍といわれる米国市場開拓のために、米国で開かれた展示会に出品した。同社のプリンターは、印字音がとても静かであり、福祉機器分野で先行する欧米メーカーのものよりも性能面で高い評価を受け、予想以上に早く輸出の話が決まった。
米国の企業だけでなく、展示会に訪れていた英国やドイツ、フランスなど欧州の企業からも、点字機器販売について提携の話がきている。小さな市場でも参入の仕方を工夫することで、ビジネスを成り立たせることができる。採算が取りにくいとされていた福祉機器分野で成功している同社の取り組みは、ビジネスチャンスを発掘して生かすことの重要性を教えてくれている。
(本田 昌彦)